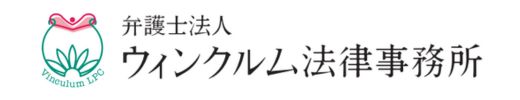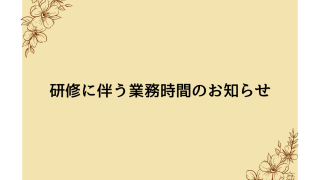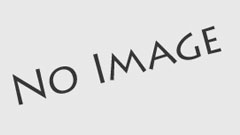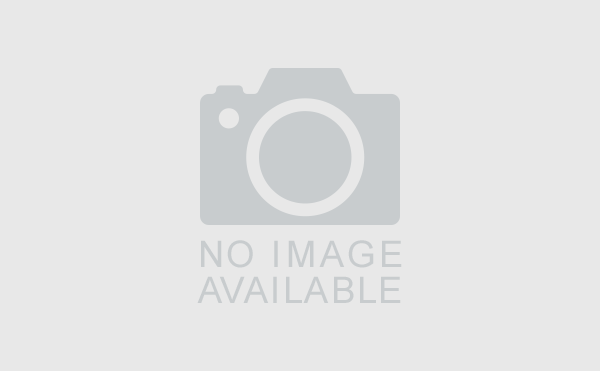子供がいない夫婦の相続について教えてください。
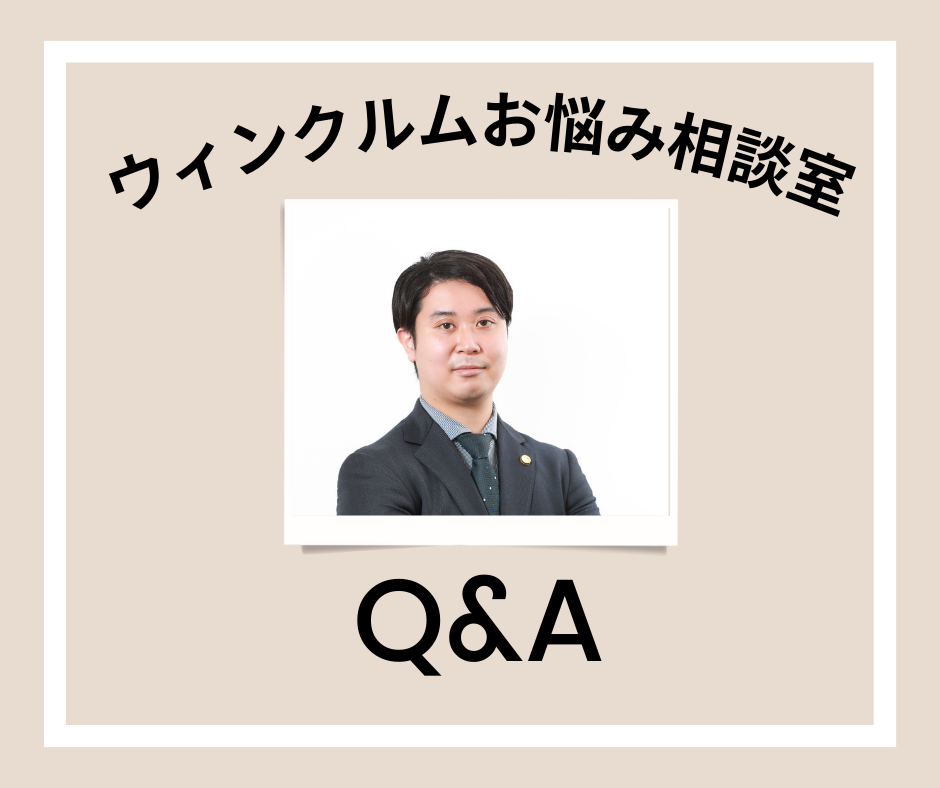
Q.私たち夫婦には子供がおりません。今は2人とも元気に過ごしていますが、今後のことを考えたときに相続はどのようになるのでしょうか。また、終活準備としてどのようなことをしておけばよいでしょうか。
A.(1)夫婦間に子供がいない場合の相続
相続を考える際には、まず誰が相続人となるのかを考える必要があります。 まず、相続人は配偶者と子・直系尊属・兄弟姉妹です。
ただし、法律婚に限られますので、事実婚の場合には配偶者に相続権はありません。
配偶者と共に相続人となる人は以下の順位で決まります。
・第1順位 子
・第2順位 親 祖父母などの直系尊属
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹
以上の順位に基づいて、上位の人から配偶者とともに相続人となります(民法889条1項)。なお、誰もいなければ配偶者のみが相続人となります。 例えば、子がいる場合は子と配偶者、子がいない場合は親(祖父母)と配偶者、直系尊属も亡くなっている場合は兄弟姉妹と配偶者になります。
今回は、子がいないとのことなので、直系尊属もしくは兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
(2)終活準備としてすべきこと
終活準備は、あなたの死後、遺された家族の負担を減らすことや、家族間のトラブルを防止するために行います。
あなたの死後に、あなたの想いを残すため、遺言書の作成をすべきです。
遺言書がなく、相続人が複数存在する場合には、共同相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割を行うことになります。
しかし、遺産分割協議は必ずしも上手くまとまるとは限りません。死後にあなたの生前の想いを代弁してくれる人はおらず、あなたの想いが十分に相続人間で共有されるとは限らないからです。
あなた自身の想いを死後に残すことに遺言書の作成はとても意味があります。
遺言によれば、法定相続分と異なる形で相続をさせることが可能です。
「すべての遺産を配偶者に相続させる」とすることもできます。
もっとも、相続人間では、法律上、遺留分という最低限度の取り分が認められています。
仮に、配偶者以外に父母が相続人である場合には、「すべての遺産を配偶者に相続させる」旨の遺言を作成したとしても、父母は配偶者に対して遺留分に相当する金銭の支払いを求めることが可能である点に、注意が必要です(民法1042条、1046条)。
ちなみに、被相続人と関係性が遠いことから、兄弟姉妹については遺留分が認められていません。そのため、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、全財産を配偶者に取得させる旨の遺言が大きな意味をもつことになります。
また、遺言書を使えば、配偶者が先に他界した場合も想定して、「遺言者は、配偶者が先に他界した場合には、配偶者に相続させるとした財産を○○に相続させる。」というように、配偶者が死亡した場合の差配まで可能です。
このように、遺言書では、自身の想いを実現する方法は多様にあります。遺言書は、単純に相続財産の割り振りをするだけではなく、多様な形を実現できることも大きな魅力になります。
投稿者プロフィール

- 神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。
最新の投稿
 お知らせ2025年4月1日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】
お知らせ2025年4月1日【研修に伴う業務時間変更のお知らせ】 お知らせ2025年3月31日2025.3 ニュースレター
お知らせ2025年3月31日2025.3 ニュースレター お知らせ2025年3月31日子供がいない夫婦の相続について教えてください。
お知らせ2025年3月31日子供がいない夫婦の相続について教えてください。 ウィンぐるめ探検隊2025年3月10日【三宮ぐるめ】STAND JAPA SOBA HANAKO
ウィンぐるめ探検隊2025年3月10日【三宮ぐるめ】STAND JAPA SOBA HANAKO
ご相談はこちらから
相談しやすい弁護士があなたのお悩みを解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。